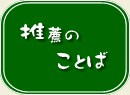 |
|
昔、山賊が長更(ながふけ)の部落を荒らしたので、弘法大師さんが山賊を山の穴におしこめ、大きな石でふたをし、そのふたに爪で地蔵様をかいて祭った。村の人は9月18日村中でお参りをする。(玉城町、71、女) |
|

|
 |
一見、ただの岩かと思う
|
 |
|
 |
現在は、はなそげ地蔵は玉城町世古の南東にあり、小俣町の飛地,、新村の近く。大仏山公園の南西側の山の懐に、ひっそりとある。(下欄のマップ参照)
道脇の斜面に直径2メートルほどの花崗岩があり、その上面に、1メートルほどの背丈のお地蔵さんが線彫りされている。線に色を挿しているわけではないので、良く見ないとわからない。
今では9月18日に地区の代表者がお参りする と教えてもらった。(2005年)
|
 |
|
|
|
 |
岩の表面には- |
 |
|
 |
推薦の言葉が語るごとく、岩は穴の蓋みたいな感じではあるが、普通の岩にも見える。
岩の表面には確かに、地蔵さんが描かれている。さて、右の写真、みなさんにはどう見えますか?
画像にマウスをかざすと像が現れるが、これは当グループの一人が拓本で像を採り、写真上で石に重ねてみたもの。
お姿がよく見えないから良いので、これでは有り難味が薄れる、と感じる方もおられるだろう 。
|
 |
|
|
|

|

|
 |
拓本で採った線彫りの像
|
 |
|
 |
地蔵さんの姿を写し取ってみたのが左の像である。
拓本でとり、これを撮影、パソコンに入れて修正し、白黒を反転してみた。
花崗岩の自然石だから表面が粗く、細部は良くわからない。
鼻の部分は僅かに凹んでいて、「鼻そげ」の感じになっている。
〔拓本〕石碑の文字などを写し取る技法です。石の表面に湿らせた和紙を置き、上から布で押すと、石の凹んだ部分では紙が凹みます。この上から油性の墨汁を含ませたタンポン(大きなてるてる坊主状のもの)でたたくと、表面全体は黒くなるが、凹んだ部分に墨が付かず、その部分が白く浮き出てきます。
|
 |
|
|
|
|
|
あなたのオススメ意見をおまちしています。
意見を書き込む方は、「オススメする」からどうぞ。
|
|  |
|
 |
 HOME
/ アクセスマップ
HOME
/ アクセスマップ
|